昭和39年通達の解説の三・四段落目、「「相続関係説明図」の様式等は〜」を読んで、相続関係説明図の作成方法を確認してください。
なお、相続関係説明図を添付した場合の戸籍等の原本還付については、新たに通知がでています。
昭和39年11月21日民事甲第3749号民事局通達
相続を証する書面の原本還付について
[要旨]
相続関係登記事件に添付した相続関係を証する書面(戸籍又は除籍の謄本等)の原本還付を当該書面の謄本を添付せずして請求する手続。
[本文]
相続による権利移転の登記及び相続人よりするその他の登記の申請書に添付された不動産登記法第41条もしくは第42条の規定による書面(戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益の証明書、遺産分割の協議書(遺産分割の審判書(又は調停調書)を含む。)等)の原本還付を請求する場合において、その謄本に代え、別紙の振り合いで作成された「相続関係説明図」を提出した場合には、便宜原本還付の取扱をしてさしつかえないものと考えるので、この旨貴下登記官に周知してしかるべく取り計られたい。
[解説]
登記申請書に添付して提出した申請書の付属書類について、その原本の還付を受けるには、当該書類の原本とともに、その書類を謄写し、その末尾に相違ない旨を申請人において奥書記名、押印した謄本を添付して請求すべき(不動産登記法施行細則第44条の11第1項)ものとされていることは周知のとおりである。
ところで、相続による権利移転の登記及び相続人により申請するその他の登記事件についての申請書に添付する相続又は相続人の身分を証する書面(戸籍又は除籍の謄(抄)本)、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書(審判書又は調停調書を含む。)等)について、申請(嘱託)人が右の書面の原本を他日他の登記所に再使用する等の目的でその還付の請求をしようとする場合には、右の書類の全部についての謄本の作成を要するのであるが、相続関係は複雑であって、その相続又は身分を証する書面は多岐にわたりその数も多量となるのが通常であり、申請人の謄本作成に要する手続並びに経費の負担も尠くないし、他方、登記所においても、右謄本を原本と対照してしなければならない調査確認等に要する手数が相当の負担となり軽視できないので、かねてより申請人の負担の軽減と併せて登記事務の能率的処理を図るため、該手続の簡易化について各法務局の意見も徴し慎重に検討されていたのである。
今般、右手続の簡易化についての成案が得られ、右の謄本に代えて「相続関係説明図」(通達「別紙」参照)を提出した場合には、便宜、原本還付の取扱をしてさしつかえない旨通達されたのである。
なお、この取扱のなされることによる実益は非常に大きいものであると考えられる。
「相続関係説明図」の様式等は通達の別紙に示されたところにより作成することを要するのであるが、その記載は、被相続人については、最後の住所(登記簿上の住所と最後の住所が同一でないときは、それらを併記する。)相続開始の時期(死亡又は死亡したと見做された日)及び事由を記載し、氏名に(被)と冠記して被相続人であることを明らかにし、中間の相続人(例えば、通達「別紙」に例示の乙某)及び代襲相続の場合における被代襲者については、その氏名を記載した傍らに相続開始の時期(死亡又は死亡したと見做された日)及び事由又は相続権を失った者である旨を記載する(例えば、相続人の欠格事由該当者については、「欠格」と、推定相続人の廃除をされた者については、「廃除」と記載する。)等の振り合で作成されるのが適当であるとされたものである。
なお、推定相続人中相続の放棄をした者がある場合には、その旨の氏名を記載した傍らにその旨を記載し(例えば、「放棄」と記載し)、共同相続人中特別受益者及び遺産分割により当該登記の申請物件に関する権利を取得しない者については、その旨を氏名を記載した傍らに例えば「特別受益者」又は「分割」と記載するものとされ、当該登記の申請物件に関する権利を取得した者については、その氏名の記載の傍らに住所及び生年月日を記載し、その氏名に(相)と冠記して、申請物件に関する権利の取得者である旨を明らかにする趣旨で示されたものである。
次に、相続又は身分を証する書面が登記申請の代理権限を証する書面をも兼ねている場合(例えば、未成年の相続人に代わって法定代理人(親権者又は後見人)が登記を申請する場合において相続を証する書面たる戸籍の謄本でその法定代理権限をも証する場合等)に、当該書面を還付できるか否かについてはこの通達には触れていないので、この場合、当該書面は還付できないものと解されよう。
昭和40年8月3日民事甲第1956号民事局長通達
相続及び住所を証する書面の原本還付について
[要旨]
相続に関する所有権移転登記の申請書に添付された「相続関係説明図」に登記権利者の住所として、不動産登記法施行細則第41条に規定された住所証明書の住所が明確に記載されている場合は、相続及び住所を証する書面は、便宜原本還付して差し支えない。
[照会]
相続による所有権移転の登記に添付された、不動産登記法第41条の規定による書面等の原本還付の取り扱いについては、昭和39年11月21日付民事甲第3479号の貴職の通達によって取り扱っていますが添付の「相続関係説明図」に、登記権利者の住所を明らかに記載することによって、不動産登記法施行細則第41条の書面も、便宜原本還付の取り扱いをしてもさしつかえないように考えられますがこの取り扱いが認められないものか、お伺いします。
なお、右の取り扱いが認められるならば、同細則第44条の11第2項の記載は「相続及び住所を証する書面は還付した。㊞」と、記載すべきであると考えますがあわせてご指示をお願いいたします。
[回答]
昭和40年6月25日付登第304号をもって問合せのあった標記の件については、不動産登記法施行細則第41条の規定により添付すべき書面における住所が、「相続関係説明図」に明確に記載されている場合には、前段、後段とも便宜意見のとおり取り扱ってさしつかえない。
[解説]
申請書に添付すべき不動産登記法施行細則第41条の規定による住所証明書の原本還付を請求するには、原本と相違ない無塩を記載した謄本を申請書に添付する必要があることはいうまでもない(同細則第44条の11第1項)。また、「相続関係説明図」の提出による相続関係の添付書類の原本還付を認めた趣旨は、相続人の身分を証する書面は、内容が複雑で部数も多数となり、これらの書面の原本還付を求めるために謄本を作成することは、申請人にとって大きな負担となるのでこれを軽減するとともに、登記官の調査事務の能率化のためにも有意義と考えられたのである。そして、「相続関係説明図」に登記権利者たる相続人の氏名、生年月日のほかに住所の記載をもされているのは、登記権利者の特定せしめるためであった、住所が記載されていても住所証明書の原本還付までも認める趣旨ではないのである。
しかして、この「相続関係説明図」に関する通達(昭和39、11、21民事甲第3749号)によっては、住所証明書の謄本を作成することなくしてその原本還付を認めることはできないのである。
ところで、所有権移転登記等に登記権利者の住所証明書が、必要とされるのは、登記権利者の真正を担保し、架空人名義に所有権の登記がなされるのを防止するのにある。したがって、「相続関係説明図」に登記権利者(相続人)の住所として細則第41条の規定による住所証明書の住所が明確に記載されており、これを登記官が照合して確認すれば、右の趣旨を逸脱することにはならないといえる。それで「相続関係説明図」を認めた趣旨からも相続に関する登記に限り、住所証明書もとくに謄本を作成することなく、原本還付をしてさしつかえないと解されるのである。これによって相続に関する登記について「相続関係説明図」と共にその簡素化と能率化を期することができると思われる。
つぎに、登記官が、申請書の添付書類の原本還付するときは、その謄本が原本と相違ないことを確認してから、その謄本に原本還付した旨を記載して捺印することになっている(細則第44条の11第2項。)それで本件の場合は、住所証明書の謄本はないのであるから、「相続関係説明図」の左下部に「相続及び住所を証する書面は還付した」。と記載し、登記官が押印すべきこととしたものである。
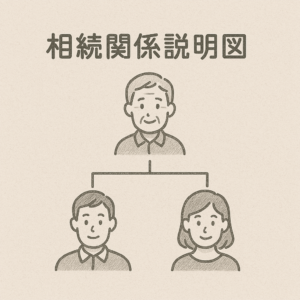
コメント