
実体的には〜、手続的には〜、というように本ブログ内に書かれていることがありますが、どういう意味ですか?



チャッピー(ChatGPT)に聞いてみました。
下記がその答えです。
実体法と手続法の違いは、法律の機能と目的に関係します。以下、民法と不動産登記法を例にして説明します。
1. 実体法 (Substantive Law)
実体法は、権利や義務の内容そのものを規律する法律を指します。
具体的には、誰がどのような権利や義務を持つか、その権利がどのように発生し、変更され、消滅するかを規定します。
民法における実体法の例:
- 所有権 (民法第206条)
「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物を使用し、収益し、処分する権利を有する。」- 所有者が何をできるのか(使用、収益、処分)を規定。
- 契約 (民法第521条以降)
- 契約がどのように成立し、どのような効力を持つかを定めます。
不動産登記法との関係:
不動産登記法の規定によって登記される所有権や抵当権も、民法上の規定によって定められる「権利」が基礎になっています。つまり、民法が不動産登記法の基盤です。
2. 手続法 (Procedural Law)
手続法は、実体法に基づく権利や義務を実現・保護するための手続を規定します。
例えば、権利があることを対外的に証明したり、権利を適切に行使したりする方法を定めます。
不動産登記法における手続法の例:
- 登記申請手続
不動産登記法第7条~第8条では、登記申請に必要な手続や必要書類について規定しています。- 例えば、不動産の所有権移転を登記するためには、登記原因証明情報(売買契約書など)が必要。
- 登記記録の内容
登記法は、登記簿に記載される情報やその管理方法を規定します。
民法との関係:
例えば、民法の規定に基づいて所有権を取得した場合でも、その権利を第三者に対抗するためには、不動産登記法に基づき登記が必要です(民法第177条)。
まとめ:民法と不動産登記法の観点
- **民法(実体法)**は、権利や義務の「内容」を規定し、不動産の所有や契約の成立条件などを定めます。
- **不動産登記法(手続法)**は、民法で認められた権利を「実現」または「対外的に主張」するための手続を定めます。
両者は相互に補完的な関係にあり、実体法がなければ権利そのものが存在せず、手続法がなければその権利を他人に示したり保護したりすることができません。
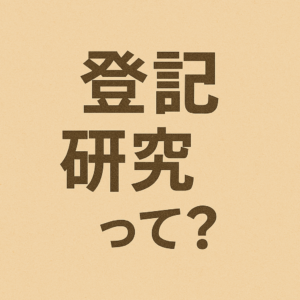
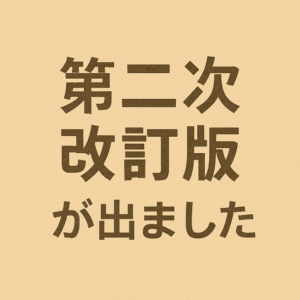
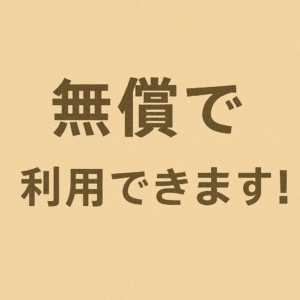

コメント